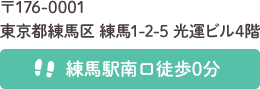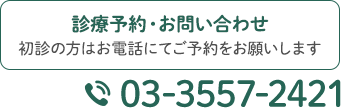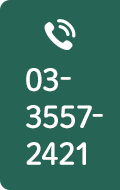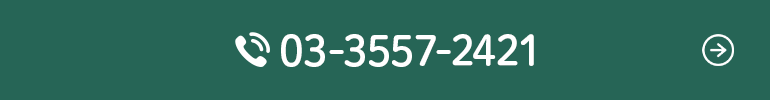心療内科クリニックからのメッセージ:あなたの睡眠、見つめ直してみませんか?
「最近よく眠れない」「朝スッキリ起きられない」――そんな睡眠のお悩みは、多くの方が抱えているご相談です。当クリニックにも、不眠で来院される方がたくさんいらっしゃいます。
あなたに必要な睡眠時間は、あなただけのもの
「〇時間眠らなければ不健康」といった話を聞くこともあるかもしれません。しかし、実は**「何時間眠れば健康的か」という決まった答えはありません**。最新の研究では、必要な睡眠時間や最適な睡眠パターン(朝型・夜型など)は人によって大きく異なり、中には3時間以上の個人差があることも分かっています¹。
大切なのは、たとえ短時間でも、「日中に疲労感がなく、元気に活動できること」。これが、あなたにとって「ちょうど良い睡眠」のサインです。ご自身の睡眠を「問題ない」と思っていても、客観的な睡眠計測では隠れた睡眠不足が見つかるケースもありますので、もし気になる場合は専門家にご相談ください²。
当クリニックでは、患者様一人ひとりのライフスタイル(仕事、家庭、趣味など)を丁寧に伺い、「今の睡眠がご自身に合っているか」を一緒に考えていきます。
睡眠を妨げる意外な要因
睡眠障害は、うつ病や統合失調症、認知症といった他の病気に伴って現れることもあれば、独立して発症することもあります。特に現代の都市生活では、シフト勤務や家庭環境の変化だけでなく、私たちの身近にあるものも睡眠に影響を与えることがあります。
例えば、就寝前のアルコール摂取は一時的に寝つきを良くするように感じられますが、その後の睡眠の質を低下させ、睡眠リズムを乱すことが研究で示されています³。また、スマートフォンの使用、特にSNSやゲームなどは、画面から発せられるブルーライトが睡眠を妨げたり、脳を興奮させたりするため、寝る前の使用は控えることが推奨されています⁴。
「薬」と「生活習慣」のバランスが大切
睡眠の治療においては、一時的に睡眠薬を使用することで、つらい不眠を和らげ、心身の健康を取り戻すことができます。特に重度の不眠症では、薬物療法は非常に有効な選択肢です。
しかし、長期間にわたる安易な睡眠薬の使用(特にベンゾジアゼピン系薬剤)は、依存性のリスクや、日中の眠気、ふらつき、転倒、そして中止時の不眠の悪化などが指摘されています⁵。最近の研究では、新規にベンゾジアゼピン系薬剤を使い始めた方の約9%が8ヶ月以上継続使用していたという報告もあります⁶。長期使用と認知症リスクの関連については研究者間で議論が続いており、確定的な結論は出ていませんが、注意深く見守る必要があります⁵。
当クリニックでは、不眠の治療は**「車の両輪」**のように、「薬物療法」と「生活習慣の改善」を並行して進めることが最も望ましいと考えています。特に、不眠症に対する最も効果的な非薬物療法として確立されているのが、「認知行動療法」です⁷。これは、睡眠に関する誤った考え方や行動パターンを修正していく治療法で、お薬に頼りすぎずに健康的な睡眠を取り戻すのに役立ちます。運動や寝室環境の整備も、非薬物療法の大切な要素です⁷。
ご自身の睡眠に不安を感じたら、ぜひ一度ご相談ください。一人ひとりに合った最適な治療法を一緒に見つけていきましょう。
参考文献
-
TSUKUBA JOURNAL. 自覚している睡眠時間や睡眠の質は「当てにならない」. https://www.tsukuba.ac.jp/journal/medicine-health/20250117141500.html
-
株式会社S'UIMIN. 最新研究で分かった“主観と実態のズレ” 自分の睡眠を誤解してる?. https://www.suimin.co.jp/column/Report_pnas
-
日本肥満症予防協会. 不眠対策のお酒は逆効果 アルコールが睡眠メカニズムを乱す原因に. https://himan.jp/news/2015/000047.html
-
塩野義製薬. 薬を使わない治療(非薬物療法)|不眠症の治療方法. https://wellness.shionogi.co.jp/insomnia/acceleration/acceleration1.html (ブルーライトに関する情報を含む)
-
青山メンタルクリニック. 2025年 最近の睡眠薬. https://www.aoyama-mc.com/topics06/
-
CareNet.com. 日本におけるベンゾジアゼピン長期使用に関連する要因. https://www.carenet.com/news/general/carenet/48518
-
CareNet.com. 不眠症併存患者に対する非薬物療法の有効性. https://www.carenet.com/news/general/carenet/40450
睡眠障害

「眠れない」にもいろいろなタイプがあります
「眠れない」と一言で言っても、その悩み方は人それぞれです。例えば、布団に入ってもなかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚めてしまう、朝まで眠ったはずなのに「眠りが浅い」と感じてスッキリしない、といった様々なタイプがあります。また、実は眠れない原因として、「睡眠時無呼吸症候群」(眠っている間に呼吸が止まってしまう病気)や、「概日リズム睡眠障害」(体内時計と実際の生活リズムがずれてしまう状態)、「むずむず脚症候群」(寝ようとすると脚に不快な感覚が現れ、動かしたくなる病気)といった、隠れた病気が潜んでいることもあります。これらの病気が原因で不眠が起きている場合、安易に睡眠薬を服用すると、かえって症状を悪化させてしまう可能性もあります。
体や心の不調も睡眠に影響します
私たちの体や心の状態も、睡眠に大きく影響します。例えば、アレルギーによるひどいかゆみで眠れなかったり、うつ病などの心の病気が原因で不眠になることは非常に多く見られます。このような場合、ただ睡眠の質を改善するだけでなく、根本にある病気をきちんと治療することが、ぐっすり眠れるようになるためのカギとなります。
まずは、あなたの睡眠のお悩みを教えてください
一方で、病気が原因ではないケースも少なくありません。枕などの寝具が合っていなかったり、寝室の環境(明るさ、音、温度など)、あるいは日中の運動不足やカフェインの摂りすぎといった生活習慣を見直すだけで、眠りの質が驚くほど改善することもあります。「眠れない」というお悩みがある場合は、まずはその原因に何らかの病気が隠れていないかを専門的にしっかり調べることが大切です。その上で、あなたに合った最適な解決策を見つけ、一緒に取り組んでいきましょう。
睡眠に関するどんな小さなお悩みでも構いません。まずは当クリニックにご相談ください。
不眠症の原因
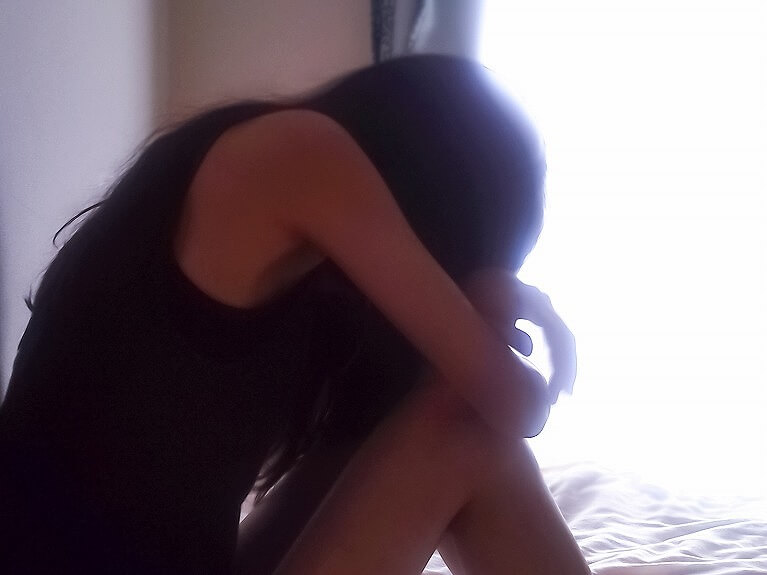
不眠症の種類
なかなか眠れない入眠障害、途中で目が覚めてしまう中途覚醒、熟睡感が乏しい熟眠障害、起床時間より早く目覚めてしまう早朝覚醒の4タイプに分けられます。日本睡眠学会では、こうした不眠が週に2回以上あって、少なくとも1ヶ月以上その状態が持続していて、苦痛を感じる、あるいは社会生活や職業的機能が妨げられている状態を不眠症と定義しています。
入眠障害
寝つきが悪く、眠るまで2時間以上かかるタイプです。心配なことやストレスなどで起こりやすいのですが、眠ってしまえば朝までしっかり眠れます。
中途覚醒
寝つきはいいのですが、夜中に2回以上目が覚めてしまうタイプです。熟睡感に乏しい傾向があります。
熟眠障害
眠りが浅く、十分な睡眠時間をとっていても熟睡した感じがしません。高齢者や神経質な方に多いとされています。
早朝覚醒
すぐに眠れますが、起床時間の2時間以上前に目が覚めてしまい、そのまま眠れなくなります。高齢者やうつ病の方に多い傾向があります。
不眠症の原因
さまざまな要因がありますし、それが複雑に作用して発症している場合もあります。
心理的要因
不安、イライラ、人間関係などの悩み
身体的要因
ホルモンバランスの変化、頻尿、皮膚炎によるかゆみなど
更年期障害やアトピー性皮膚炎、前立腺肥大などによって起こるケースが多くなっています。
環境的要因
季節の変わり目、引っ越し、異動や入学、転職など環境の変化
生活習慣的要因
飲酒、喫煙、カフェインの摂取過多など
眠る直前までスマートフォンを操作していることによる入眠障害も近年増えています。特にエナジードリンクやストロング系アルコール飲料なども、大きな睡眠障害の契機となります。また夕方以降のコーヒーや紅茶の摂取なども間接的な不眠の要素になります。
不眠症の治療
不眠症の治療:あなたに合った「眠り方」を見つけるために
「眠れない」というお悩みを解決するためには、大きく分けて「生活習慣の改善」と「薬物療法」の二つのアプローチがあります。患者様の不眠の原因やライフスタイル、そして何に一番お困りかによって、最適な治療プランは大きく変わってきます。
ぐっすり眠るための生活習慣のヒント
まずは、ご自宅でできる生活習慣の工夫から始めてみましょう。これらは、あなたの睡眠の質を高めるための大切な土台となります。
1. 毎朝、同じ時間に起きて太陽の光を浴びましょう
人間の体内時計は、実は24時間よりも少し長めに設定されています。このずれを毎日リセットしてくれるのが、朝の光です。 毎朝、できるだけ同じ時間に起きて、カーテンを開けて太陽の光を浴びる習慣をつけましょう。曇りや雨の日でも、外の光を浴びることで体内時計は調整されます。寝る時間は神経質にならなくても大丈夫ですが、「起きる時間」を一定に保つことが、質の良い睡眠への第一歩です。
2. 朝食をしっかり摂りましょう
起床後1時間以内に朝食を摂ることで、体全体が活動モードに切り替わり、体内時計も整いやすくなります。腸の働きを活発にし、体を目覚めさせるためにも、朝食は欠かさずに食べましょう。
3. 適度な運動を習慣にしましょう
日中の適度な運動は、血行を良くし、体の代謝を上げることで、夜の深い眠りにつながります。ただし、寝る直前の激しい運動は、かえって体を興奮させてしまうので控えましょう。就寝前は、軽いストレッチなど、リラックスできる程度の運動がおすすめです。
4. 昼寝は午後3時までに30分以内が目安です
日中に強い眠気に襲われた時、短い昼寝は心身のリフレッシュに効果的です。午後3時までに、長くても30分以内にとどめるのがポイント。これ以上長く寝てしまうと、夜の睡眠に影響してしまうことがあります。
5. 入浴は就寝の約3時間前までに済ませましょう
体温が一度上がって、それがゆっくり下がる時に人は眠りにつきやすくなります。そのため、寝る3時間くらい前までに入浴を済ませ、体を芯から温めておくと良いでしょう。ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、心身ともにリラックスでき、スムーズな入眠につながります。
6. 寝る前のパソコンやスマートフォンの使用は避けましょう
スマートフォンやパソコンの画面から出る強い光(ブルーライト)は、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑えてしまいます。眠る時間が近づいたら、これらのデバイスの使用は控えるのが賢明です。一般的には、就寝の2時間前からは使用しないことが推奨されています。
7. 眠くなってから布団に入りましょう
「〇時になったから布団に入らなきゃ」と無理に寝ようとすると、かえって目が冴えてしまうことがあります。眠れないまま布団の中で過ごす時間が長くなると、「布団=眠れない場所」という悪いイメージがついてしまうことも。「眠い」と感じてから布団に入るようにすることで、スムーズに眠りに入りやすくなります。
薬物療法について
生活習慣の改善を試してもなかなか眠れない場合や、不眠の症状が強い場合には、薬物療法を検討します。睡眠薬には、寝つきを良くするタイプ、夜中に目が覚めるのを防ぐタイプ、眠りを深くするタイプなど、様々な種類があり、不眠のタイプによって適した薬が異なります。例えば、薬の効き始める速さや持続時間も、不眠のタイプに合わせて選ぶことが重要です。また、不眠の原因となっている病気(うつ病など)や、不眠に伴うイライラなどの症状によっては、抗うつ薬、抗不安薬、抗精神病薬、漢方薬などが検討されることもあります。
ただこの薬物療法の効果は個人差が多く、Aさんに効果のある薬がBさんに効果があるとも限りません。年齢や生活スタイルを考慮しながら適切な薬物療法を提案するのが精神科専門医の仕事です。
大切なのは、医師から指示された用法や用量をしっかりと守って服用することです。自己判断で薬の量を増やしたり、飲むのをやめたりすると、かえって症状が悪化したり、体に負担がかかることがあります。
ご自身の判断で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。一緒に、あなたにとって最適な治療法を見つけていきましょう。